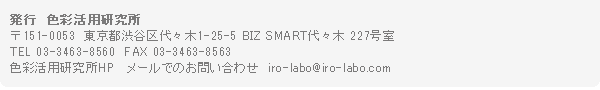こんにちは!サミュエルの三浦です。
今年は例年になく桜が早く咲いてしまい、
皆さん、ちょっぴり駆け足のお花見だったのではないでしょうか。
私も出勤の時に、桜並木の下を自転車で走り抜けながら
お花見していました。
これから一気に新緑の季節に向かい、
もう少しすると、さわやかに晴れ渡る空色をバックに、
色とりどりの、こいのぼりが泳ぐ5月になりますね。
こいのぼりは、「鯉が龍になって天に昇る」という伝説から、
男の子の成長を祈るものです。
「黒の真鯉はお父さん、赤の緋鯉はお母さん、青の子供鯉」
「青の子供鯉」というのは、青(緑)は、春と木を意味し、
生命の活動を始める春、そしてすくすく伸びる木から、
子供の成長を表しているそうです。

この鯉の色は「五行説」に基づいてつけられています。
五行説とは、「木・火・土・金・水」の五元素が盛衰循環して、
この世の中が動いているという、中国の考え方。
この五元素には、色も対応していて、「青、赤、黄、白、黒」の
五色があてはめられています。
こいのぼりと一緒に飾られる「吹流し」は、この5色。
魔よけの意味があるんですよ。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
私は、色の定期講座を担当していたとき、よく講座の導入で、
季節の色や、旬の色の話題を紹介してから本題に入っていました。
カラー検定対策講座だと、講師としてはどうしても
「色の理論をしっかり教える」ことに意識がいきがちですが、
色を教える講師の本当の役割は、
「日常の色に目を向けるきっかけづくり」なのではないかと思います。
日本には四季の移り変わりがあるので、
その色をその時に肌で感じて楽しむのも、なかなか楽しいものです。
そして、日本の色の話はけっこう奥が深く、一般の方向けの講座でも人気です。
先日開催したシニア世代向けの講座では、色名の由来の話を
熱心にメモしていらっしゃいました。
色の講師を目指す方は、「色の雑学知識」を持っていると、
何かと皆さんに楽しんでもらえますよ。
まずは、あなたの興味のある分野を掘り下げて、
楽しみながら知識をインプットしてみてくださいね。
私は、国文科出身で古文専攻だったので、
平安時代の色の話を語らせると、長くなってしまいます!!
重ねの色目とか、恋文の色の話とか…。
こちらのGW企画も、よろしければお役立てくださいね。
![]()
オススメ講座
![]()
◆ GWスペシャル企画『色彩に学ぶ日本文化』
日本独自の色彩文化を紐解きながら日本古来の感性を学びます。
5/6(月・祝)13:00〜16:00 / 受講料:6,000円(税込)
***************************************************************************
★今回のメルマガはいかがでしたでしょうか?ご感想をお待ちしております。
⇒感想はこちら